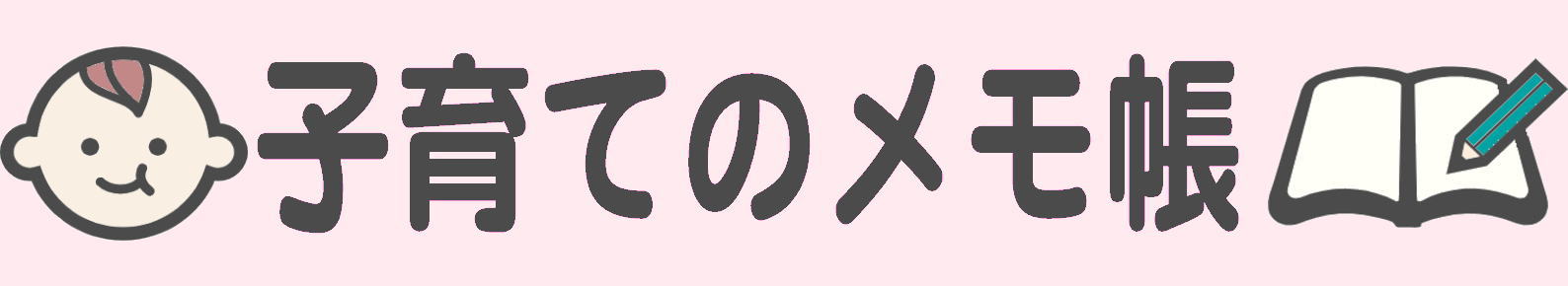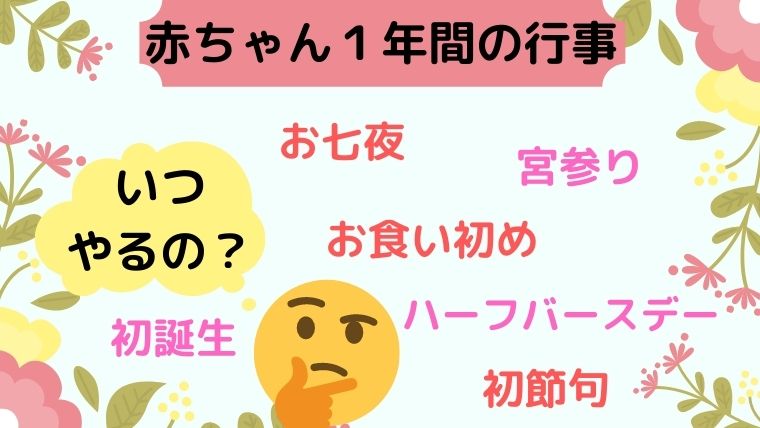赤ちゃんが生まれて1年間は、行事が盛りだくさん!
そんな赤ちゃんの1年間の行事を時期ごとにまとめました。
お七夜(生後7日)
赤ちゃんが生まれて初めての行事。
それが、お七夜(おしちや)です。
お七夜
- 赤ちゃんが生まれて7日目におこなうお祝い
- 命名所に赤ちゃんのお名前を書いて披露します
命名書は、赤ちゃんの名前を書く用紙です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
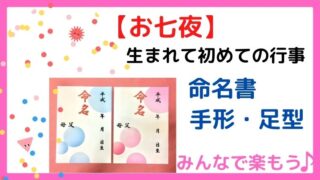
宮参り(生後1か月頃~)
次の行事はお宮参りです。
お宮参り
- 赤ちゃんと初めて神社にお参りに行く行事
- 正式には、男の子なら生後31日目、女の子なら生後32日目に参拝(地域によって異なります)
ただ、生まれてから1か月くらいとなると、あっという間です。
赤ちゃんとお母さんの体調がまだ安定していないこともあります。
1か月健診が終わり、母子とも体調的に安定してきてからの参拝でOKです。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
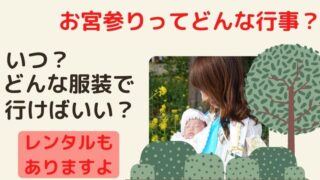
お食い初め(生後3~4か月頃)
次はお食い初めです。
お食い初め
- 赤ちゃんが一生食べ物に困らないようにという願いを込めて行うお祝い
- 時期は、生後100日目、または120日目
お食い初めの日は、絶対に100日目、120日目でなくてはならないということはありません。
母子ともに体調の良い日、家族の都合のいい日でOKです。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
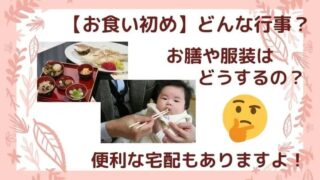
ハーフバースデー(生後6か月)
次は、ハーフバースデーです。
ハーフバースデー
- 生後6か月のお祝い
バースデーは誕生日のお祝いですが、ハーフバースデーはその半分の6か月、生後6か月のお祝いです。
ハーフバースデーは、バースデーと同様、ケーキなどを用意します。
そして、赤ちゃんの記念写真を撮るというふうな楽しいイベントです。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
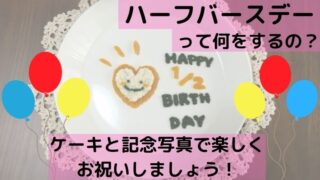
初誕生(生後1年)
次は初誕生、1歳の誕生日です。
初誕生
- 満1歳の誕生日をお祝いする行事
- 一升餅を風呂敷にくるんで赤ちゃんの背中に背負わせる(地域差あり)
- 選び取りという遊びがある
初誕生は、満1歳の誕生日をお祝いする行事です。
初誕生のお祝いの仕方は地域によって異なります。
一升(約1.8kg)のお米でついた一升餅を風呂敷にくるんで赤ちゃんの背中に背負わせるという行事があります。
そのほか、さまざまな道具を置いて、赤ちゃんが何を選ぶかで、赤ちゃんの将来を占う選び取りという遊びもあります。
普通に1歳のバースデーケーキを買って祝っても結構です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。

初節句(初めての3月3日又は5月5日)
最後に紹介するのは初節句です。
初節句
- 初節句は、生まれた赤ちゃんが初めて迎える節句のお祝い
- 女の子は桃の節句(3月3日)、男の子は端午の節句(5月5日)
節句とは、暦(こよみ)の上で、季節の変わり目となる日のこと。
これまで紹介した赤ちゃんの行事は、生後何か月頃というふうな感じ日程でした
初節句は日付指定の行事となります。
そのため、1~2月生まれの女の子や3~4月生まれの男の子は、生まれて間もない時期に初節句の日を迎えてしまうことになります。
そうした時期は、母子の体調が良いとも限りませんし、赤ちゃんの首も座っていなかったりします。
そんな場合は、初節句を遅らせることもありです。
初節句を1年遅らせることを検討する目安としては、地域によりますが
- 宮参りが終わってから
- 初めてのお正月を迎えてから
というふうしているところもあります。
初節句の時期は、母子の体調を見ながら祖父母などと相談して決めるようにしてください。
まとめ
赤ちゃんが生まれて1年目は、いろんな行事が盛りだくさんです。
| 生後7日 | お七夜 |
|---|---|
| 生後1か月頃~ | 宮参り |
| 生後3~4か月頃 | お食い初め |
| 生後6か月 | ハーフバースデー |
| 生後1年 | 初誕生 |
| 3月3日、5月5日 | 初節句 |
行事は、母子の体調を最優先にして、いろんな行事を楽しくやってみてください。